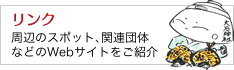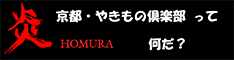真葛焼は幕末、仁清写しの名手と評価される宮川長造が青木木米に師事し陶器全般を習い、観勝寺安井門蹟から「真葛」という号を授かったことに始まる。円山公園より南に位置するところに長造が窯を開き、円山公園一帯の地が「真葛ヶ原」と呼ばれていたことからその名を受けた。
長造には4人の息子がいたが、長男の長平が早逝。四男の寅之助が家を継ぎ、「真葛香山」として、薩摩藩士小松帯刀などの後ろ盾のもと、明治3年横浜の地に移住し、開窯。貿易港だった横浜の地の利から、「マクズウェア」の名で、海外輸出を手掛けて大成功を収めた。しかし、3代目香山が昭和20年横浜空襲で戦災死し、弟が4代目を継承するも、昭和34年、4代目の死去とともに横浜の真葛の歴史は幕を閉じる。
一方、宮川長造の本家筋にあたる宮川治兵衛の家系は、古くは江戸貞享年間、近江の国宮川村より京都に出てき、知恩院門前において陶器の焼継ぎや釉薬を扱う「焼継所」を商っていた。五条坂に移ってからはさらに繁盛を極め、文政年間(1820年代)のころ「赤こん香齋」の代より本格的に作陶も手掛け、横浜真葛家との技術交流も行っていたという。以来、代々香齋を継承し、4代目が半床庵久田無適齋宗匠に茶道の手ほどきを受けてからは茶陶の世界を中心に作陶する。
現当主は、六代目宮川香齋。香齋の継承者は代々養子筋が多く、宮川さんもその一人である。宮川さんは京都に生まれ、東京造形大学美術学部では彫刻を専攻していたが、「作ったものを人に使ってもらいたい」という思いから、卒業後は工芸の世界へ進もうと、6年ほど焼き物の修業を経験。独立を考えていた頃に、縁があって真葛家に入ったという。
「この家に入った時にはある程度の焼き物の技術は備わっていました。しかし茶道具は寸法や形それぞれに決まりごとが細かくある世界。流儀の中で違和感のないものを作っていかないといけません。先代からもその辺を厳しく言われましたし、自分自身も常に心がけていました」
「この家に入った時にはある程度の焼き物の技術は備わっていました。しかし茶道具は寸法や形それぞれに決まりごとが細かくある世界。流儀の中で違和感のないものを作っていかないといけません。先代からもその辺を厳しく言われましたし、自分自身も常に心がけていました」
「限定されたなかで想像力を働かせること」が作陶するうえで大事だと、宮川さんは話す。真葛焼の大きな特色は、長造の初代から受け継がれた「藁灰釉」という釉薬にある。藁灰、土灰、長石の三種類から成る釉薬で、柔らかい質感が茶陶の世界によく合うという。
「それぞれの腕やセンスもありますから、代によって全部が同じというわけでもありませんし、時代の流れによって作るものも違っています」
これまでにいかにいい作品を見てきたかどうか、さらには人間性も陶器に現れるという。宮川さんはそんな陶器の機微に触れながら、真葛焼の看板である藁灰釉や風合いを守る。
「釉薬や茶碗の形、筆使いは守っていきたい。それがなくなってしまうと、家の風がなくなってしまう。そのうえで、私は使っていて心地いいもの、上品なもの、すっと目の中や心の中に入ってくるものを作っていきたいですね」個展ではお客さんと接する機会がありますが、自分の作品がお客さんに使われていると、実感することほど嬉しいことはありません。使ってもらうためには、誠実なものを作らなければいけないということも、改めて感じます。ごまかすことなく、誠実なものを作る。そういう思いで今後も作り続けたいと思っています。
個展ではお客さんと接する機会がありますが、自分の作品がお客さんに使われていると、実感することほど嬉しいことはありません。使ってもらうためには、誠実なものを作らなければいけないということも、改めて感じます。ごまかすことなく、誠実なものを作る。そういう思いで今後も作り続けたいと思っています。