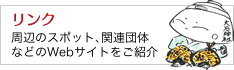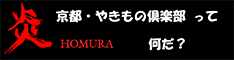「この技だけは、誰にも負けません」と、75歳を超えた今でも、ろくろを回す姿が印象的だ。
それは、ただ“熟練”という言葉では片付けられない。手のしわや、土の動きを見つめる目には、絶え間ない努力が隠れているのだろう。
雲楽窯の三代目として生まれた齊藤武司さん。平時なら順調に継ぐ道があっただろう。だが、戦争のために学徒動員にあい、戦後の混乱は、陶器制作の再開を困難にさせていた。
「私自身、負傷のため入院していました。退院後、どうやって生きていこうかと考えたとき、ある恩師の言葉を思い出したんです。“戦後は、自分のために生きろ”と。もう一度、陶器を始める決心がつきました」
それから5年間、父に師事しながらも、京都中を修行に渡り歩いた齊藤さん。勤め先が廃業になるなどのつらい経験もしたが、どこの修行先であっても、努力し続けることは惜しまなかった。
「それこそ、死に物狂いでしたよ。独立したい、技術を身につけたい、その一心でした。工場には、朝六時の開門とともに入って、帰るのは、深夜1時ごろ。門が閉まってるので、塀を乗り越えて、帰ったものでした。」
そんな努力から、徐々に齊藤さんの作品が認められるようになり、昭和25年には、五条坂にて独立開業を果たした。
「そこまで努力を続けられたのは何だったのか?今だからこそなんですが、戦時の軍事教練があったからやろうって思うことがあります。あの時は、死ぬことを覚悟してたし、命をかけることを学びました。だから、戦争が終わって、自分のために、家族のために、命をかけようって思ったとき、それが、どういうことをすればいいのかが、わかるんです。」
独立開業後は、独自の釉薬の開発に力を注いだ齊藤さん。登り窯が当たり前だった時代に、電気窯を取り入れ、そこで「青抹陶」という釉薬を生み出す。うっすらと青みがかった上品な色合いが特徴の釉薬だ。
「電気窯を使うと言い出した当時は、みんなから“あほや”と言われましたね。けれど、自分が求めるものに対して、それが従来の方法であるかないかは、関係ないと思てます。登り窯で何度挑戦しても出なかった色が、電気窯で実現できたんやったら、電気窯使うのは当たり前やと」
もうひとつ、齊藤さんには“あほや”といわれたことがあるという。それは、五条坂から、山科の清水焼団地へ移ってしばらくたってのこと。展示即売という形で、工房に店を出したことだ。
「“なんで窯元が店をだす必要があるねん、あほか”、って。でも、店を出した途端、ずいぶんお客さんが来てくれたんです。」
千円から一千万円という、一般食器から花瓶、飾壷まで、雲楽窯では、幅広い陶器が揃う。工房はまた、見学可能で、ろくろから、絵付け、釉がけ、焼成にいたるまで、全工程を見ることができる。
「やはり、どこで誰が、どういう風に作っているかを伝えることが大事なんでしょう。陶器の魅力をより正確に知ってもらうことができますから」
今では主流となった、電気窯に展示即売。それを先駆けて始めてきた齊藤さん。そこには、命をかけてきた、齊藤さんのゆるぎない力が根底を流れている。
私が店を開店してもうすぐ30年が経とうとしています。今では多くの窯元が店を出すようになり、清水焼団地も、作家や職人だけの町でなく、観光客の方や陶器好きの方が訪れることのできる場へと変化しています。
清水焼の魅力は、ろくろ、整形、絵付け全ての工程が、狂いもなく正確になされる、手技だと思っています。その技に会いに、足を運んでいただければ幸いです。